-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
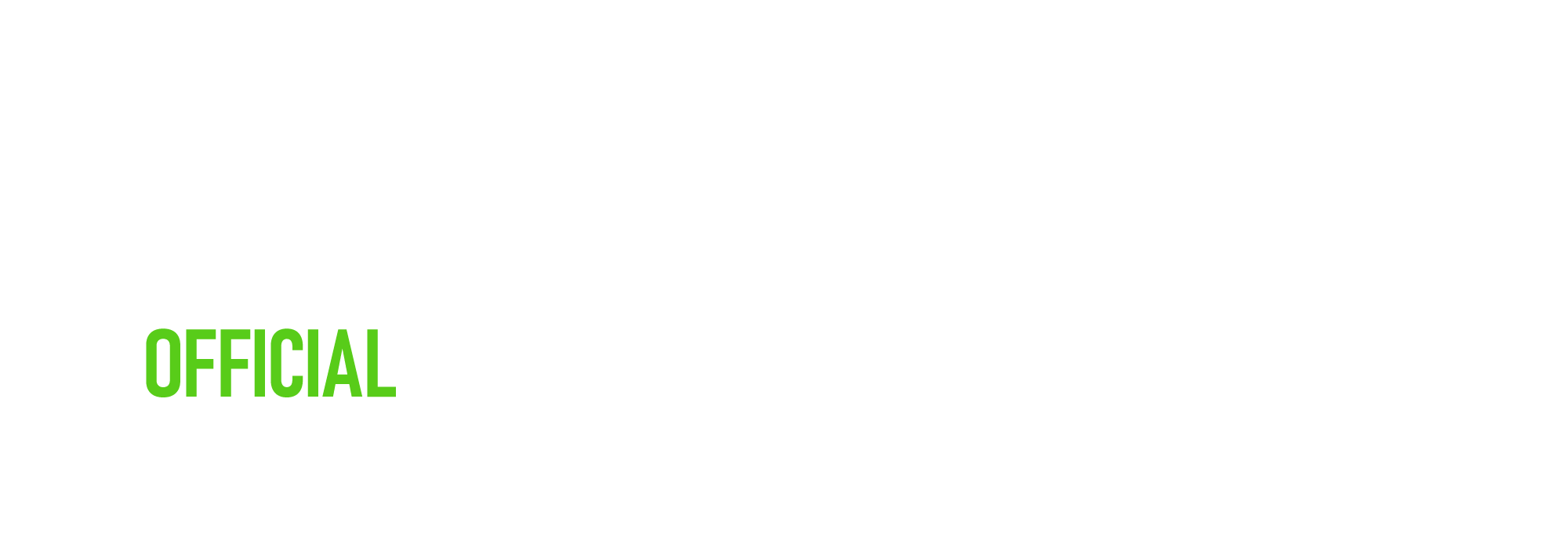
皆さんこんにちは!
新田興業、更新担当の中西です。
“段取り”で8割決まる
解体工事業は、建物を壊すだけの仕事ではありません。安全に、近隣に配慮し、分別し、適正に処理し、次の建設へバトンを渡す“始まりの工事”です。ところが現代の解体現場では、工事量が増える一方で人材不足と高齢化が進み、現場が回りにくくなっています。最大の課題は「人が足りない」だけでなく、「段取りが組める人が足りない」ことです。⚠️
■ 若手が入りにくい理由:危険・汚いイメージが先行
解体は粉じん、騒音、振動、重機、落下物など、危険要因が多い仕事です。さらに、アスベストなど有害物質のイメージもあり「怖い」「大変そう」と見られがちです。😣
実際には、養生の標準化、散水設備、集じん、重機の高性能化、法令対応の整備などで安全性は高まっています。しかし、その姿が伝わらなければ採用市場では不利なままです。
■ 高齢化が進むほど“属人化”が深刻化する
解体は、現場ごとに条件が違います。狭小地、隣家が近い、道路が細い、電線が低い、地下に埋設物がある、構造が複雑…。同じ木造でも、築年数や増改築で壊れ方が変わります。🧠
こうした現場で品質と安全を守るには、事前調査・手順設計・重機の選定・搬出導線・養生計画・分別計画など、段取りが要です。ところが段取りのコツがベテランの頭の中にあると、引退とともに会社の強みが失われます。📉
■ 技能継承を阻む「教える時間がない」問題
解体は工程が短く、スピードが求められます。現場は“今日壊して明日搬出”のようにテンポが速く、教育が後回しになりがちです。😥
しかも解体は危険作業が多く、任せる側も慎重になります。若手に任せられない→経験が積めない→成長が見えない→離職、という悪循環が起きやすい業種です。
■ 解決の方向性①:段取りを“見える化”して教育資産にする
解体は段取りで8割決まります。だからこそ、段取りを仕組みに落とします。✅
・現地調査チェックリスト(構造、狭小、埋設、近隣、電線、搬出)📋
・工法選定の基準(手壊し、重機、圧砕、ワイヤー、切断)
・養生・散水・集じんの標準仕様
・分別計画(木、金属、コンクリ、廃プラ、石膏ボードなど)
・近隣説明のテンプレ(工期、時間、騒音、連絡先)📣
これを案件ごとに記録し、次の現場に活かすと、属人化が減り、若手も学びやすくなります。📚✨
■ 解決の方向性②:分業で職長を守り、教育時間をつくる
職長が現場・近隣・元請け・産廃・書類まで全部抱えると疲弊します。🧩
・産廃の手配・マニフェスト管理は事務が支援
・写真整理・書類作成をテンプレ化
・搬出計画と車両手配を内勤が補助
職長が現場管理と安全に集中できるほど、事故が減り、若手に教える余白が生まれます。⏰✅
■ 採用の見せ方:成長ルートと安全教育を言語化する
若手が知りたいのは将来像です。🌱
「何年で重機に乗れる?」「資格は?」「危険作業はどう教える?」
これを採用ページやSNSで具体的に見せるとミスマッチが減ります。現場の雰囲気、教育の様子、保護具、粉じん対策、1日の流れなどを発信すると安心感が増します。📱✨
■ 人材課題はKPIで回す 📊
・応募数/面接数/入社数
・3か月、6か月、1年の定着率
・資格取得(車両系、玉掛け、足場、フルハーネス等)
・教育チェックリスト達成率
数字が見えると改善が続きます。✅
■ まとめ:段取りが強い会社は、現場が安定し紹介が増える
解体工事業の現代の課題の中心は“人”と“段取り力”です。段取りを仕組みに落とし、分業で職長を守り、教育を見える化できれば、品質が安定し、元請け評価が上がり、紹介が増えます。🌟
次回は、安全管理・法令対応(特にアスベスト)と働き方の課題を掘り下げます。🚧✅
■ ミニ面談で定着率を上げる 🗣️
月1回、10分でも面談をすると離職が減ります。
「今月できるようになったこと」「困っていること」「来月の目標」を言語化して記録するだけで、育成が“見える化”されます。📒
■ 現場を支える“小さな改善”チェックリスト ✅
・朝礼で「今日の最重要リスク」を1つだけ共有する
・終業前に5分だけ“終わり点検”(養生・散水・危険物・写真)をする
・搬出計画は前日までに確定し、当日の変更を減らす
・近隣対応は“窓口一本化”し、現場が対応し過ぎない
小さな改善の積み上げが、事故と残業と手戻りを減らします。⏱️✨
新田興業では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。
皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
新田興業、更新担当の中西です。
近隣対応とクレーム予防:説明・掲示・記録のテンプレ
クレームの8割は情報不足から。事前の周知、現場の掲示、要望の記録が揃えば、感情的な摩擦は激減します。本稿はテンプレ群(挨拶文、掲示、要望シート、日次報告)を丸ごと提供。
________________________________________
1. 戸別挨拶テンプレ
ご挨拶
このたび、〇〇邸の解体工事を実施します。
工期:〇月〇日〜〇月〇日(9:00–17:00)※高音作業は11時前後
対策:散水・防音シート・通路清掃(1日3回)
ご不明点は下記までご連絡ください。
責任者:〇〇(000-0000-0000)
2. 要望シート
お名前 ご住所 ご要望 希望連絡方法 受付日
TEL/メール/不在票
例:「洗濯物の外干しは10–12時を避けたい」「車の出庫は毎朝8:30」
3. 掲示板テンプレ
工事名:〇〇邸 解体工事
期間:〇/〇〜〇/〇(予備日含む)
責任者:〇〇(000-0000-0000)
本日の作業:本体解体/基礎撤去/整地 など
対策:散水/防音/誘導員
4. 日次レポート(近隣向けQR)
• Googleフォーム等で日次の作業内容・翌日の予定・発生音の時間帯を共有。
• 苦情は受付番号で追跡、対応期限を明記。
5. 事例と効果
• 要望シート導入で、洗濯物苦情ゼロ。作業時間の入替で工程延長なし。
• QR日報で“見えない不安”が減少、ポジティブ声掛けが増える。
6. まとめ ✨
近隣対応は情報の非対称を埋める仕事。テンプレ+記録でブレない運用を。次回は騒音・振動・粉じん対策を測定とログで実装。
新田興業では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。
皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
新田興業、更新担当の中西です。
産業廃棄物の分別・運搬・最終処分:リスクとコスト♻️🚛
“何を、どう分け、どう運ぶか”。解体のコストと信頼は分別精度で決まります。本稿は材質別の実務と混合廃棄の落とし穴、マニフェストの運用、処分場の選定までを体系化。写真・数量・受入証の“三点セット”で証跡管理を固めます。📸
________________________________________
1. 材質別の要点 🧪
• 木くず:含水率・釘残り・塗装の有無。乾燥仮置きで重量を抑制。
• コンクリ(ガラ):サイズ分け(〜80mm、〜200mm)、鉄筋残りを磁選で回収。
• 金属:鉄・非鉄に分け、銅線は別系統で価値回収。
• 石膏ボード:紙・芯材の混入管理。硫化水素対策(通気・計測)。
• ガラス・陶磁器:袋破れ対策、ケガ防止。
• 混合廃棄:最後の受け皿だが単価が高い。減らす設計がコスト鍵。💰
2. 分別ヤード設計 🏷️
• 色分け(木=緑、金属=青、ガラ=灰、石膏=黄、混合=赤)。
• 動線:作業→仮置き→積込を直線化。バック走行を最小化。
• 雨対策:屋根or防水シートで重量増を防ぐ。
3. 運搬と車両手配 🚚
• 2t/4t/10tのシャトル設計。路地奥は2tで集め、ヤードで10t積替え。
• 飛散防止:シート掛け、積載量の法定範囲遵守。
4. マニフェスト運用と証跡 📑
• 電子マニフェスト推奨。収集運搬・処分の受領確認をリアルタイムで。
• 三点セット:数量表+写真+受入証を案件フォルダで紐づけ。
5. 事例:石膏ボード多量現場 🧱
• 改修履歴で二重貼り。分別ヤードに専用パレットを設け、破砕最小化。
• 混合廃棄比率を15%→5%に削減、処分費▲28%。
6. まとめ ✨
“最後は混合で”をやめる。最初に分ける設計で、コストも評価も改善します。次回は近隣対応のテンプレを公開。🏘️
新田興業では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。
皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
新田興業、更新担当の中西です。
テナント退去やリニューアルでは、短工期・夜間作業・ビル管理ルールが重なります。騒音/粉じんの閾値、搬入出動線、共用部の養生、テナント営業時間に合わせたタイムスライスが成功の鍵。ここでは“3つの線(音・埃・動線)”を同時に制御する実務を、チェックリストとテンプレで示します。⏱️
________________________________________
1. 着工前の管理調整 📋
• 管理会社の工程承認:作業時間・音出し可能時間・搬出窓の確保。
• 共用部養生計画:エレベータ・床・壁コーナー、復旧の責任範囲を文書化。
• 建築/電気/空調の協議:止水・残置設備・ダクト汚染対策。
2. 作業の“タイムスライス”設計 ⏳
• 21:00–23:00:静音作業(養生・撤去準備)。
• 23:00–02:00:高音作業(ブレーカー・はつり)。
• 02:00–05:00:積込・搬出・清掃。
• 05:00–06:00:検査・共用部復旧・臭気確認。
3. 粉じん・臭気・騒音管理 🔇
• 負圧集じん機を開口部に設置、作業区画はポリ養生でエアロック。
• 散水+ミストで粉じんを抑制。
• 臭気は溶剤使用時に活性炭フィルタ、作業後はオゾン処理の可否を事前合意。
4. 廃棄物の分別と搬出 ♻️
• 夜間の搬出動線は台車→エレベータ→仮置き→トラックを直線化。
• 床材/天井材/金属/ガラス/混合の色分けコンテナでミス防止。
5. テンプレ:夜間作業掲示 🧾
夜間作業のお知らせ
日時:〇月〇日〜〇月〇日 21:00–6:00(高音作業 23:00–2:00)
作業:内装撤去・下地はつり
対策:負圧集じん・散水・共用部養生・夜間清掃
連絡:責任者 〇〇(000-0000-0000)
6. 事例:駅直結ビルの原状回復 🚇
• 駅の始発前に搬出完了が必須→増員で02:00までに高音完了、残りは清掃と復旧に集中。
• 床点検口を活用し、ダクト・配線のトレースを不具合なく実施。
7. まとめ ✨
短工期の肝はタイムスライスと動線直線化。夜間の音・埃・臭気を定量管理し、共用部の原状回復まで含めて“翌朝問題なし”を作ります。次回は産業廃棄物の分別・運搬・最終処分へ。♻️
新田興業では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。
皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
新田興業、更新担当の中西です。
鉄骨造(S造)は、“つないでいるものをほどく”作業です。接合は溶接・高力ボルト・リベット等。火気と高所のリスクを管理しながら、順序立てた切断→吊り降ろし→分別を行います。揚重は荷重と重心、旋回範囲、風の3点が命。ここでは、都市部の中規模S造を想定し、切断計画・防火養生・玉掛け手順・クレーン選定までを現場目線で解説します。🔥🧯
________________________________________
1. 接合の見極めと解体手順 🔍
1) 調査:図面・現地で接合種別(溶接/ボルト)・柱脚(露出/埋込)を特定。
2) 仮設:先行足場・防炎シート・火花飛散防止板、消火設備の配置。
3) ボルト外し/切断:梁→小梁→デッキ→ブレース→柱の順。倒れ込み防止の“残し”を計画。
4) 揚重:玉掛け角度と荷重分散、重心マークで安定化。
5) 分別:鉄骨・デッキ・スラブ(RC)・断熱材を区画分けし、搬出。
コツ:“最後の1本をどこに残すか”を全員で共有。声掛けと合図をルール化。📣
2. 火気管理・防火養生 🔥
• 火気作業許可:日次発行、責任者・時間・場所を明記。
• 防火養生:耐火シート、火花受け、下階の養生二重化。
• 消火体制:粉末消火器×複数、バケツ・ホース、火の元確認は退場時に2回。
3. 揚重計画とクレーン選定 🏗️
• アウトリガー設置条件:道路占用の有無、地耐力、暗渠の位置。
• 機種:25t〜50tラフテレーンクレーンが一般的。旋回範囲と上空電線の有無を確認。
• 合図法:統一手信号+トランシーバー、合図者を固定。
4. 事例:S造3階・延床600㎡・市街地 🏙️
• 夜間火気禁止のビル管理規定→昼間切断、夜間搬出に工程分離。
• 風観測を導入(風速計)。瞬間風速10m/sで作業中止基準を明文化。
• デッキ下の断熱材飛散に注意し、湿潤化と袋詰めで管理。
5. よくあるミスと予防 ⚠️
• ボルト残りの見落とし→切断時の急な回転。→目視+指差呼称、カラーチョークで“外し済み”表示。
• 玉掛け角度過大→荷重集中。→2点→4点へ切替、スリング長を見直す。
• 火花の養生不足→下階のカーペットに焦げ。→不燃ボードで二重遮蔽。
6. まとめ ✨
S造は順序と合図の工事。火気・高所・揚重の三位一体を抑えれば、安全・静音・高効率が両立します。次回は内装スケルトン/原状回復の短工期段取りを解説。🕘
新田興業では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。
皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
新田興業、更新担当の中西です。
RC解体は“壊す”ではなく壊し分ける。騒音・振動・粉じんの三重管理のもと、クラッシャー/ブレーカー/ワイヤーソーを使い分け、鉄筋分離と再資源化を最大化します。⚙️
________________________________________
1. 工法の選択肢と適用条件 🔧
• クラッシャー(圧砕):騒音・振動は中、粉じんは散水で抑制。梁・柱に有効。
• ブレーカー(打撃):能力高いが振動・騒音が大。学校・病院近隣は時間帯限定。
• ワイヤーソー/コア抜き:静的切断、振動極小。コスト↑だが近隣条件が厳しい場合に有効。
2. 養生と静音計画 🔇
• 防音パネル+二重シート、開口部は負圧集じん。
• 散水ノズルの固定化で継続的に粉じんを抑制。
• 測定点(敷地境界2点+出入口1点)を設定し、日次ログを掲示。📈
3. 鉄筋分離と搬出設計 ♻️
• 圧砕→鉄筋の露出→グラップルで回収→磁選→ガラはサイズ別に。
• 仮置きヤードを区画線で分け、積込み動線を直線化。
• 10t車が入れない場合、4tシャトルで回数設計。🚛
4. 事例:RC3階建・前面4m道路 🏢
• 切断→吊り降ろしで躯体をブロック化。
• 1階商業テナントの営業時間に合わせ、高音作業は早朝集中。
• 鉄筋回収を徹底し、再資源化率95%を達成(社内KPI)。
5. 安全と品質のKPI 🎯
• 災害ゼロ、クレームゼロ、測定基準内、再資源化率90%以上、工程遵守。
• KPIは現場掲示し、日次でチェック。達成状況を近隣にも共有。
6. まとめ ✨
RC解体は静かさと分別の競技。工法を混ぜて設計し、測定・記録で見える化すれば、高難度でも“静か・きれい・早い”は実現できます。次回は鉄骨造。切断・防火・揚重の三位一体を解説します。🔩
新田興業では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。
皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
新田興業、更新担当の中西です。
最も件数が多く、近隣との距離が近いのが木造解体。手壊し→小型機→分別→搬出の型を、粉じん・騒音の最小化と安全の観点で解説します。
________________________________________
1. 基本フロー
1) 仮設足場・防音/防炎シート、散水設備の設置。
2) 屋根材・建具・設備の手外しで軽量化。
3) 小型バックホウ搬入、梁→柱→壁の順に分別解体。
4) 材質ごとの仮置きゾーン(木・金属・ガラ・石膏)。
5) 搬出(2t/4t)、場内清掃、第三者目線の完了検査。
2. 近隣対策の型
• 時間帯宣言:高音作業は午前11時前後に集中、洗濯時間の配慮。
• 散水ログ:開始/終了時刻と散水量を記録→苦情時の根拠。
• 通路清掃:午前・昼・退場前の3回清掃で印象が一変。
3. 安全の要点 ♀️
• 屋根上は親綱+フルハーネス。
• 重機周囲の立入禁止と誘導員。
• 釘・ガラスの二次災害に備えた保護具。
4. 分別と再資源化 ♻️
• 木くず:含水率と釘残りに注意。釘外しの工夫で受入可否が変わる。
• 石膏ボード:可燃混入厳禁、破砕・飛散の抑制、パレット保管で搬出効率UP。
• 金属:磁選・手選別で価値回収。
5. 10日スケジュール例(延床25坪・路地奥)️
• 1日目:仮設足場・シート、掲示・近隣確認。
• 2〜3日目:手壊し(屋根材・建具・設備)。
• 4〜6日目:小型機で本体、分別徹底。
• 7〜8日目:基礎・土間、静的破砕剤併用で振動抑制。
• 9日目:搬出集約、清掃、境界確認。
• 10日目:整地・最終確認・写真引渡し。
6. よくある失敗と回避策 ⚠️
• 雨天で粉じん対策を怠る:逆に泥跳ねの苦情。→散水+養生の調整と通路養生を厚めに。
• 仮置きスペース不足:混合化で処分費増。→先に庭・駐車場の仮置きを確保。
• 搬出車の時間帯ミスマッチ:通学時間帯に被る。→学校カレンダー反映の工程表。
7. まとめ ✨
木造は段取りと気配りが品質。静音・粉じん・安全のバランスを取り、“見られている現場”を意識すれば、クレームゼロは現実的です。次回はRC造の解体。鉄筋とコンクリを切って、挟んで、分ける現場術を紹介。
新田興業では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。
皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
新田興業、更新担当の中西です。
アスベストは“有無の確認”で終わりません。レベル区分で対策と工期、費用が大きく変わるため、調査→計画→周知→実施→記録を一気通貫で設計することが不可欠です。本稿では、戸建〜中規模施設までに通用する現実解をまとめます。🧰
________________________________________
1. 事前調査の進め方 🔍
• 図面・年式・材料名から疑義部位を抽出(吹付材・保温材・成形板・ボード類)。
• 目視+試料採取:想定範囲を過小にしない(二重貼り・改修履歴に注意)。
• 分析結果の反映:レベル1〜3の判定、工程の組み替え(先行除去か封じ込めか)。
2. レベル別対策の考え方 🧪
• レベル1(吹付材等):原則除去、負圧養生・集じん・入退室管理・個人防護。工期・費用への影響大。
• レベル2(保温材・断熱材等):除去または囲い込み。機械室・配管周りは動線確保が肝。
• レベル3(成形板等):適切な切断・取り外しと飛散防止。破砕を避け、湿潤化を徹底。
3. 近隣と関係者への周知 📣
• 工期・作業時間・高リスク時間帯を明記。
• 監視測定の実施、緊急時連絡フロー。
• 掲示・チラシは平易な言葉と図解で不安を下げる。📝
4. 記録とマニフェスト 📸
• 除去量の写真・袋数・重量を一致させる。
• 二重袋・ラベル・保管場所の管理台帳。
• 収集運搬・最終処分までの追跡を残す。
5. 事例:1978年竣工・学校校舎の天井材 🏫
• 吹付材の一部改修有。試料採取で含有判明。
• 夜間に負圧ゾーンを設け、動線分離。翌朝の授業に影響しない工程へ。
• 作業中は連続測定、結果を掲示板とWEBで周知。
6. まとめ ✨
アスベストは段取りと透明性が鍵。科学的根拠と記録があれば、関係者の不安は最小化できます。次回は木造住宅の解体を“静か・きれい・早い”の型で解説。🏠
新田興業では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。
皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
新田興業、更新担当の中西です。
「手続きは後で」──それが最も高くつきます。解体は届出・計画の順番を誤ると着工が遅れ、重機や人員の手配がやり直しに。ここでは、現場が止まらないための法令フローをタイムラインで解説。現地掲示や近隣説明に使える一枚サマリもテンプレ化します。🧭
________________________________________
1. タイムライン(着工6〜2週間前)⏱️
• 6週前:基本計画、構造種別・規模の確認、アスベスト事前調査の手配。
• 4週前:建設リサイクル法の事前届出準備、分別解体計画の作成。
• 3週前:道路使用/占用の必要性判定、搬出動線のルート設計。
• 2週前:近隣挨拶・掲示、騒音/振動/粉じんの計測計画、ライフライン停止申請。
重要:アスベスト調査結果を起点に他手続きが連鎖します。順番を崩さないこと。🧩
2. 主な枠組みと要点 🧰
• 建設リサイクル法:一定規模以上の解体で事前届出と分別解体が義務。工程と分別区分を明記。
• 産業廃棄物管理票(マニフェスト):収集運搬・処分のトレーサビリティ。数量・写真・保管期間。
• 騒音・振動規制:作業時間帯の設定、測定ポイントの設計、苦情時の記録様式。
• 粉じん防止:散水計画、養生シート、防じんマスク、清掃動線。
• 道路使用/占用:ゲート・仮設柵・一時停車の可否。学校時間帯の配慮。
• 労働安全衛生:墜落・重機災害・火気使用の手順、フルハーネスと先行手すり。
3. 役割分担(施主/解体会社/行政)👥
• 施主:所有権・境界・ライフライン停止・補助金申請・近隣説明同行。
• 解体会社:手続書類の作成・提出、工程表、現地掲示、計測・記録、マニフェスト運用。
• 行政/警察:届出受理、道路占用・使用許可、指導・立入検査。
4. 一枚サマリ(掲示テンプレ)🧾
工事名:〇〇邸 解体工事
工期:〇月〇日〜〇月〇日(9:00–17:00)
責任者:〇〇(連絡先:000-0000-0000)
主な対策:散水による粉じん抑制、防音シート、誘導員配置
高音作業予定:〇/〇・〇/〇の11:00前後
ご協力のお願い:車両移動のお願いをする場合は前日までに連絡します
5. 落とし穴と対策 ⚠️
• 道路幅の誤認:実測2.7mで4t不可→搬出コスト増。→事前に実測+近隣車の常駐確認。
• ライフライン未停止:メーター撤去遅れで着工延期。→申請のリードタイム表を事前共有。
• 掲示不備:苦情時に窓口不明。→現場掲示+戸別配布の二重化。
6. まとめ ✨
手続きは工程の一部。順番を守れば現場は止まらず、信頼も積み上がります。次回はアスベスト調査と除去を実務目線で掘り下げます。🧪
新田興業では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。
皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
新田興業、更新担当の中西です。
同じ30坪の木造解体でも、A社は180万円、B社は240万円──なぜここまで差が出るのか? 答えは「分別の手間」「搬出距離」「処分単価」に、養生・仮設・近隣調整といった“壊す以外の費用”が重なった設計の差にあります。本稿は、初見では読みにくい見積書を分解図として読み解き、安易な値引き交渉よりも“段取りを変えて安くする”ための実務を、テンプレ付きで徹底解説します。📑✨
________________________________________
1. 見積の骨格:5層で考える 🧱
1) 前処理費:残置物撤去・ライフライン停止・仮設電源/水道・近隣挨拶。
2) 仮設養生費:足場・防炎/防音シート・ゲート・散水設備・道路養生。
3) 本体解体費:人件費+重機稼働+アタッチメント交換。
4) 分別・搬出費:積込み・場内仮置・運搬回数(2t/4t/10t)。
5) 処分費:材質別単価(木くず/コンクリ/金属/石膏/混合)。
ワンポイント:この5層を数量×単価に落とし込めば内訳の“正体”が見えます。👀
2. 主要コストのドライバー 🚚
• 分別難易度:混構造、改修の重なり、石膏ボード量、断熱材の種類で大きく変動。
• 搬出距離と回数:現場から積込場/処分場までの距離、道路幅(2t分割か4t直付けか)。
• 処分単価:地域差大。特に石膏ボード、混合廃棄は単価が跳ねやすい。
• 時間帯制約:学校・病院近隣、夜間不可などで工期が伸びると人件費が増加。
• 仮設品質:防音シートの等級、負圧集じん、散水量など“静かさ”の設計はコストに直結。🔇💧
3. サンプル内訳(木造30坪・路地奥)📊
• 前処理・近隣挨拶:80,000
• 養生足場180㎡(防音シート付):220,000
• 本体解体(手壊し+小型バックホウ):480,000
• 積込・搬出(2t×18回):270,000
• 処分費(木くず22t、混合3t、金属0.5t):420,000
• 重機回送・諸経費:110,000
• 小計:1,580,000(税別)
同規模でも前面4m道路で4t直付け可能なら搬出回数は半減→人件費/運搬費が大幅圧縮。🚛
4. “含む/含まない”チェックリスト ✅
• 残置物(家電・畳・物置・庭石・金庫)
• 外構(ブロック・フェンス・土間・カーポート)
• 樹木(伐採/抜根/処分)
• 地中障害(基礎下のガラ・浄化槽・井戸・配管)
• 仮設電気/水道の手配と負担
• ライフラインの停止・撤去(ガス管/メーター)
• 近隣クレーム対応の人件費・追加仮設
• 測量・境界標の維持
→ ここが未記載だと“後から増える費用”の温床です。
5. 写真と数量根拠:数字は“証拠”で強くなる 📸
• 面積・体積の根拠:図面/現地採寸/レーザー距離計。
• 材質比率の仮説:木:60%、コンクリ:30%、金属:10% 等の前提を明文化。
• 搬出動線:写真+矢印で“2t縛り”の説明→施主の納得度が跳ね上がる。
6. 価格を下げる3つの戦略(値引きより設計)🧠💡
1) 残置物の事前整理:家電・衣類・書籍は施主手配の回収で混合廃棄を削減。
2) 搬出ウィンドウの確保:近隣に30分の一時停車合意→4t直付けの回数確保。
3) 分別の見える化:現地で材質別の仮置きゾーンを設計→積込み効率が改善。
7. 見積比較テンプレ 🧾
項目 A社 B社 差分/メモ
養生足場 220,000 180,000 Aは防音等級高い
本体解体 480,000 510,000 Bは重機サイズ大
搬出回数 18回 12回 Bは4t直付け可
処分費 420,000 460,000 石膏比率の前提差
諸経費 110,000 90,000
小計 1,580,000 1,540,000 仮設品質に差
判断軸は「総額の安さ」ではなく“工程と品質の整合”。静音・粉じん対策の仕様差を数字に写し取るのがコツです。🎯
8. トラブル事例から学ぶ ⚠️
• 石膏ボードの過小見積:実際は断熱改修で二重貼り→処分費+20万円。→現況写真+芯材確認を必須化。
• 地中障害物の想定漏れ:古井戸・浄化槽で+40万円。→契約時に単価表と判定プロセスを合意。
• “残置物少量”の曖昧表現:当日3LDK満杯→混合廃棄激増。→立会い写真+箱数/容積で定義。
9. まとめ ✨
見積書は現場の設計図。数字の裏にある動線・分別・仮設を読み解けば、ムリなくコストを下げ、品質を上げる打ち手が見つかります。次回は法令・許認可・届出を“止まらない段取り”の順番で整理します。📜
新田興業では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。
皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()